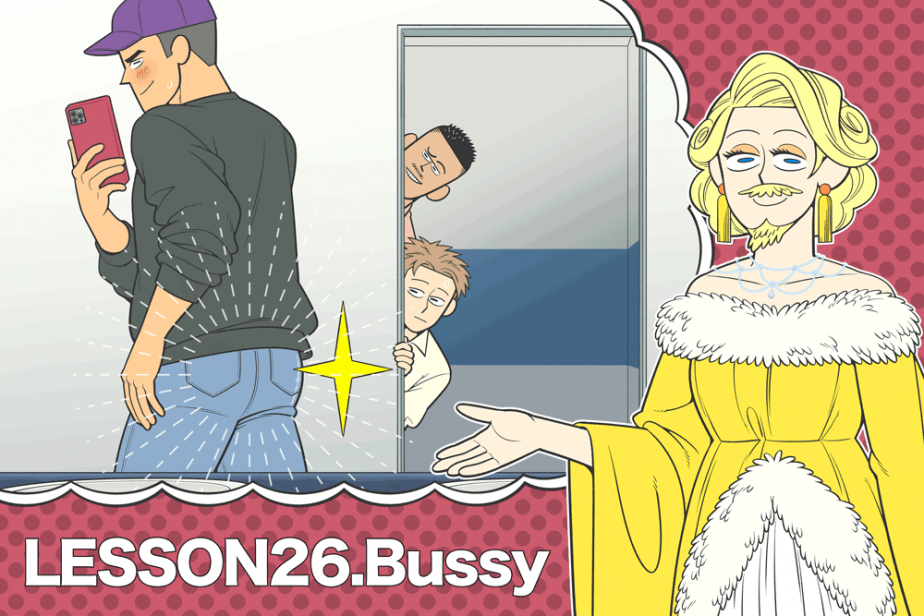主にセクシュアリティ・ジェンダーの分野で執筆をしながら、ダンサーとしても活動するレズビアン当事者の山﨑穂花さん。「わたしとアナタのための、エンパワ本」では毎月、彼女の本棚の中から、自信や安心、ありのままの尊さを教えてくれた本(=エンパワ本)を、“気付きの一文”を添えて3冊紹介。
第4回は、「居場所」と「関係性」をめぐる物語をアナタのためにピックアップ。
女として、クィアとして、生きていく中で感じてきた違和感や痛みは、決して特別なものではない。でも、その感覚を言葉にしてくれる物語に出会えることは、案外少ない。「ババヤガの夜」「ミーツ・ザ・ワールド」「光のとこにいてね」は、それぞれ違う文脈を持ちながら、境界に立つ人の孤独や、誰かとつながろうとする切実さを描いている。今月は、この3冊を通して、“ひとりじゃない”と感じられた時間を共有したい。

日本人初となる英国推理作家協会のダガー賞翻訳部門を受賞した注目の一冊。
過剰な暴力性を秘める新道依子が、ひょんなことから関東有数の暴力団組長の一人娘の運転手兼、ボディーガードとして雇われる物語が展開される。新道は社会の規範的な女らしさからは逸脱した存在であり、「女性はこうあるべき」という社会の抑圧を一身に受けて育った箱入り娘の尚子とは対照的に描かれている。抑圧的な男性社会や家父長制的な構造に対抗し、相容れない新道と尚子が生き延びるための共闘と連帯を描いたシスターフッド作品だ。
◆気づきの一文
「けれど、新道は自分と尚子が何なのか、一度も決めたことがないし、決められない」(216頁12行目)
ーーもともとは暴力団の雇われと組長の一人娘という2人は、共通の「敵」を目の前にして逃亡する。この逃亡がきっかけとなり、初めこそは真反対な2人が徐々に打ち解け合い、心の深いところで繋がる。その「繋がり」は単なる、友達、恋人、雇い人・雇われ人といった言葉では表しきれない、深い関係であるのだ。
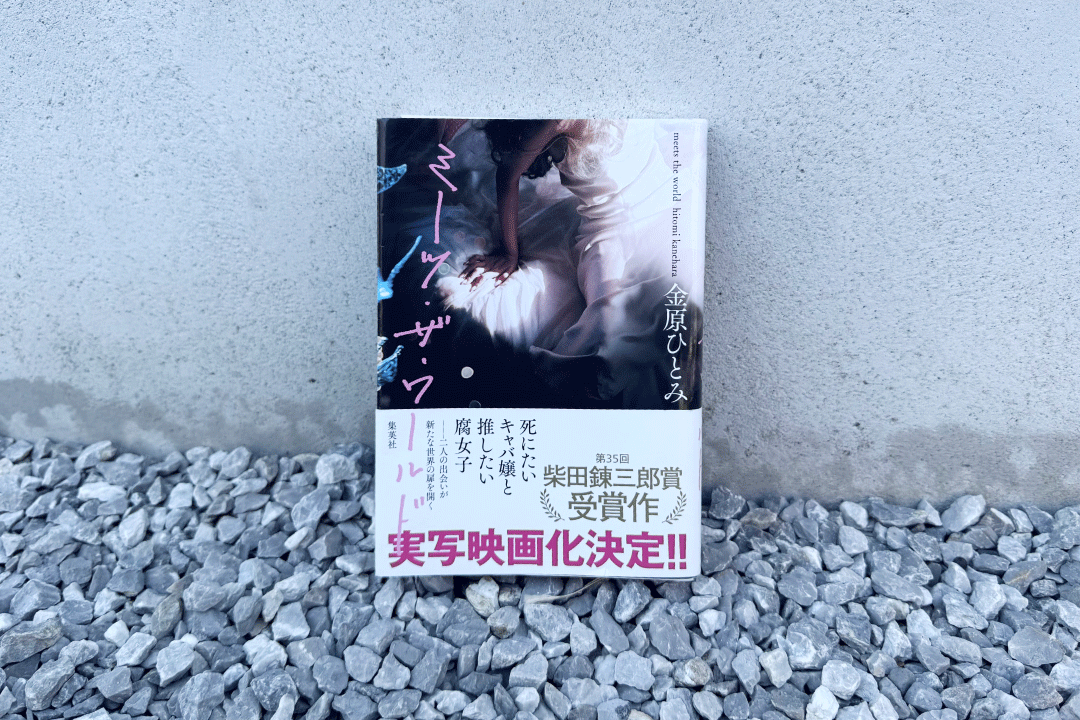
10月に映画化が決まった、死にたいキャバ嬢と推したい腐女子2人を描いた作品。
焼肉擬人化漫画をこよなく愛する腐女子の由嘉里が、人生二度目の合コンを後に歌舞伎町で酔い潰れているところを、キャバ嬢のライが見つけて家に招き入れたことから、奇妙な共同生活が始まる。一見キラキラした都会でも、その中で生きる人たちはどこか疲れていて居場所を探し求めている。ライが終始言っていた「消えたい」という言葉は必ずしも悪ではなく、むしろ自由への解放なのかもしれない。ライが消えた後の由嘉里はどのように過ごすのか、関係が破綻した先に希望を見出せるのかーー。結末は読者に委ねられる。
◆気づきの一文
「なんかさ、二次元と三次元とか、愛とか恋とか、好きとか愛してるとか、恋愛か友情かとか、恋愛か憧れかとか、世の中そういうの細分化しすぎだよ」(49頁12行目)
ーーライは由嘉里の凝り固まった常識や「男で孤独が解消される」という幻想を軽やかに解きほぐしていく。2人は職業、価値観、生活環境、生きる意欲の全てが正反対でありながら、無理に理解しようとせず、むしろ「分からなさ」を認め合ったうえで、ただ隣にいる。2人の会話からはそんな暖かさを感じる。
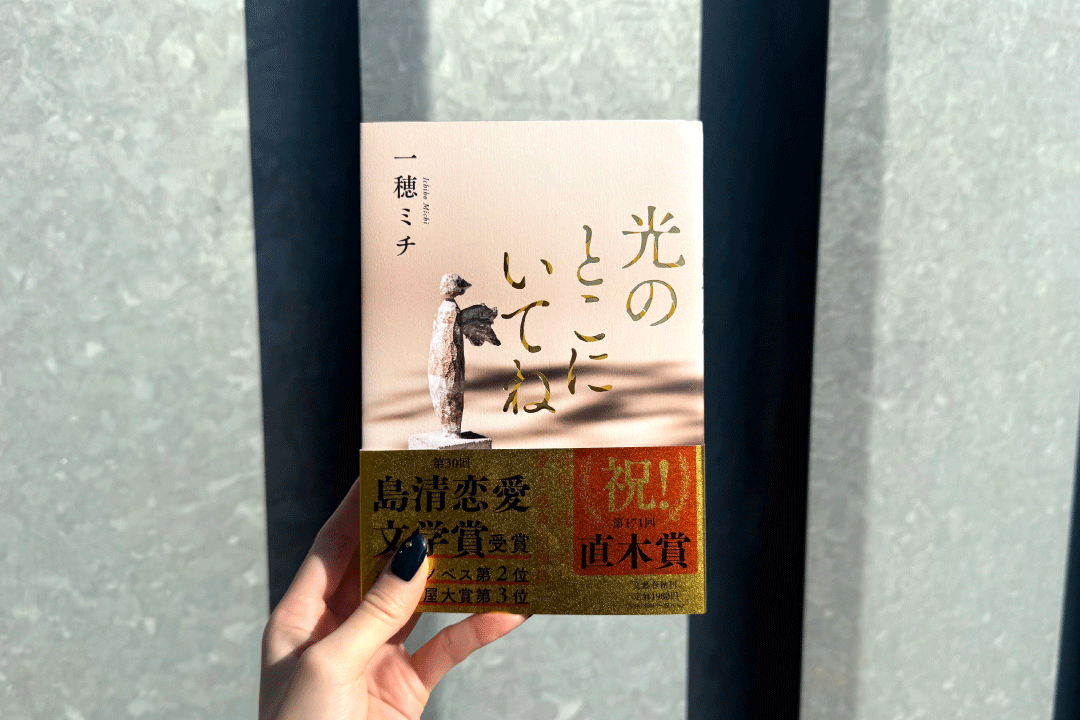
この作品は、作者の一穂さん自身が「名前のつけられない関係」を描いたといっている。
古びた団地の片隅で出会った小学生の結珠と果遠という2人の少女が、正反対の境遇に育ちながら、同じ孤独を抱え、強く惹かれ合う様子が伺える。しかし、幸せな時間は唐突に終わりを迎え、8年後、2人は名門女子校で思わぬ再会を果たすことに。作中では「光のとこにいてね」 という言葉が、異なる意味合いを持ちながら3度の別れの場面で繰り返され、常に光ではない影のところに立っている側が、相手の幸せを願う「弱々しい祈り」として表現されている。
◆気づきの一文
「私を好きでいてくれる、それだけでいいの」(361頁8行目)
ーー互いに抱きしめ合ってキスをしてから、結珠はそう言った。幼少期、高校時代とすでに2度の別れを経験している2人。お互いに家族や子どもがいて別の道を歩みながらも、再会を果たした2人には強固な愛が確実に存在する。どんな環境であれ、また別れが訪れたとしても、「好き」という事実は変わらない。
文・写真/山﨑穂花 @honoka_yamasaki
記事制作/newTOKYO